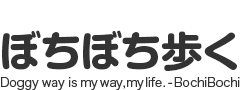東京駅構内の中央通りにある「駅弁屋 祭」グランスタ店は、日本各地の駅弁を約200種類も取り揃えている日本最大級の駅弁屋です。
日本で最初に売られた駅弁については、色々な説がありますが、1885年(明治18年)7月16日に開業した宇都宮駅で、旅館「白木屋」が握り飯2個とたくあんを竹の皮に包んで売り始めたのが最初というのが有力です。7月16日は「駅弁記念日」にもなっています。

駅弁のお供、お茶は1889年(明治22年)に静岡駅で、信楽焼の土瓶にお茶を入れて販売したのが最初と言われています。そのころは湯呑みにもなる蓋が付いて「汽車土瓶」と呼ばれていました。

2012年に「駅弁屋 祭」が東京駅の中央通路北側で営業を開始してからというもの、ここはいつも駅弁を買い求める人たちでいっぱいです。皆んな駅弁は大好きなんですね。僕も通るたびに気になってしまいます。

「毎日が駅弁祭り」のコンセプト通り、多い日は1万5,000個もの駅弁が売れるほどの賑わいです。2016年には場所を南側に移しリニューアルオープン。益々活気に溢れています。店内の駅弁厨房では、各地の駅弁の実演販売もしています。
東京駅で駅弁を買うなら、まずは「祭」には行ってみましょう。そんなワクワクの駅弁エンターテイメントスポットから、いくつか駅弁をご紹介していきます。
買って食べみたよ!オススメの駅弁。
★新潟 新津駅 三新軒
「雪だるま弁当」

1987年(昭和62年)8月に「三新軒」が販売を始めた駅弁です。「三新軒」は新潟県の新津駅(にいつえき)で1928年(昭和3年)に営業を始めた老舗です。可愛らしい雪だるまケースからは想像できないぐらい、どの具もそれぞれしっかり調理・味付けされていて、食べ応えも充分な美味しい駅弁に仕上がっています。もちろん新潟の駅弁ですからご飯はコシヒカリ100%。

★新潟 新津駅 神尾弁当
「えんがわ押し寿司」

1897年(明治30年)創業の新潟新津の神尾弁当が作る駅弁です。駅弁とは言うものの、それはカラスガレイのえんがわの押し寿司そのもの。一口頬張れば、えんがわフリークも大満足の美味しさです。脂がのっていて甘いです。もぐもぐもぐでスっと無くなる柔らかさもまた上等。

★広島 広島駅弁
「とろ〜り 煮あなごめし」

広島で「ひろしま駅弁」の名で通る、広島駅弁株式会社の駅弁です。1901年(明治34年)に創業した老舗の作る、穴子ファンなら一度は食べておきたい逸品駅弁です。広島で「ひろしま駅弁」の名で通る、広島駅弁株式会社の駅弁です。1901年(明治34年)に創業した老舗で、当時は「中島改良軒」が屋号でした。

★青森 五所川原駅 つがる惣菜
津軽めんこい懐石弁当「ひとくちだらけ」

一口ずつ24種類もの青森の食を詰め込んだ駅弁です。青森県 津軽半島の五所川原にある「つがる惣菜」が作っています。箱を開ければ、そこには食べたことも無いおかずが待っているかも。ワクワクせずにはいられないですね。

★兵庫 西明石駅 淡路屋
「ひっぱりだこ飯」

よく味の染みた本場明石だこの旨煮は、柔らかくてとても美味しいです。崩した煮穴子と錦糸玉子とともに、独自の出汁で炊かれたご飯を頬張れば、口の中いっぱいに旨味が広がります。他のおかずとともに、飽きること無く、あっという間に食べ進めることが出来ます。

★群馬 高崎駅 たかべん
「だるま弁当」

「だるま市」で売られる開運・縁起物のだるまにあやかり、1960年に販売をはじめた「だるま弁当」。今では、この赤いだるまのカタチをした駅弁がすっかり有名に。「食べ終わったら貯金箱にももなる。」ということでも良く知られている群馬の山の幸が沢山のった、しっかり味の美味しい駅弁です。

★茨城 水戸駅 しまだフーズ
「常陸牛 牛べん」

“しまだフーズ”が作る、人気の水戸の駅弁です。ご飯の上に、特製のすき焼きのタレで甘辛く煮た、茨城県のブランド牛「常陸牛(ひたちぎゅう)」がたっぷり乗っています。冷めても柔らかいその牛肉は、自前の牧場を持っている精肉業者から仕入れる、茨城県常陸牛振興協会が認定した黒毛和牛が使われています。

★神奈川 大船駅 大船軒
「“つまんでよし、食べてよし”酒肴弁当」

1898年(明治31年)創業の湘南鎌倉 大船軒が作る、おつまみにピッタリの駅弁です。出張でも旅でもシッカリご飯というよりも、あれこれ摘みながら軽く一杯やりたい時に最適な一品です。

「駅弁屋 祭」グランスタ店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9−1 セントラル ストリート(東京駅 中央通路)