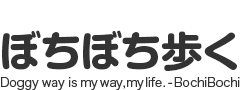流鉄(りゅうてつ)「流山線」は、流鉄株式会社が運行するローカル線。JR東日本 常磐線との接続駅である「馬橋駅(まばしえき)」から「流山駅」まで6駅、総延長5.7kmと短い距離を走る単線の鉄道です。馬橋や流山といった都市部からかなり近い場所を走るローカル線というのは他には無く貴重な存在です。

流鉄の歴史はかなり古く、営業を開始したのはなんと100年以上前の1916年(大正5年)に遡ります。流山の名産である醤油や“みりん”を輸送するために、流山町民の出資により設立したのがそのはじまりです。そんな流鉄 流山線に乗って、流山の小旅行を楽しみます。短い区間ですが、周辺には歴史がいっぱい詰まっています。

流山線は全6駅ありますが、もしや全ての駅で途中下車するかもしれませんし、往復もあるので「一日フリー乗車券(大人500円、小児250円)」を購入することにします。ちなみに通常料金だと、馬橋から流山(13分)までは片道200円ですから、途中下車して楽しむなら、一日フリー乗車券が断然お得で便利ですね。※2023年11月時点
馬橋駅(駅番号:RN1)

出発はJR常磐線から接続する「馬橋駅」から。始発のこの駅は島式ホームに2線があり、それぞれから列車は単線に出発していきます。

入線してきたのは2両編成の「流星」号です。走るのは全て西武鉄道から導入された車両で、それぞれ「流星」「あかぎ」「さくら」「なの花」「若葉」と名前が付けられ色分けされた2両5編成の列車です。

「幸谷なのは」は、流鉄 流山線の駅務係という設定のキャラクター。「鉄道むすめ」という、トミーテックが展開している鉄道関連で働く女性をモチーフにしたキャラクターシリーズの中の一人です。馬橋駅の次の駅「幸谷駅」と、列車編成の一つ「なの花」から名付けられています。
見どころ


万満寺(まんまんじ)は、鎌倉時代に作られた木造の金剛力士立像(仁王像)が有名な寺院。

立派な参道の大門(楼門)をくぐると、その奥の山門(仁王門)に金剛力士像があります。

この仁王像は、関東地方に残る仁王像としてはかなり古く、国の重要文化財にも指定されています。ちなみに楼門(ろうもん)とは、二階建てで、一階に屋根を持たない構造の門の総称です。
●王子神社

万満寺のすぐ隣りにある王子神社は、鎌倉末期に万満寺の総鎮守として諏訪神社を勧請し創建された神社です。
幸谷駅(駅番号:RN2)

次の駅は少し分かりにくい場所にある「幸谷駅(こうやえき)」。ホームは1面1線で、駅舎は「流鉄カーサ新松戸」というマンションの一階にあります。「幸谷(こうや)」とは、ここ「新松戸」周辺のもともとの地名で、今でもJR「新松戸駅」の東側は、幸谷という地名です。およそ400年前に、もともと「荒谷」と書いていたのを“幸”の字を当てるようになったといいます。

「さくら」号が入線してきました。幸谷駅のすぐ近くにはJR「新松戸駅」があるので、ここから流鉄に乗るというのも良いかもしれません。JR「新松戸駅」からは、武蔵野線の高架下を進み、小さい踏切を渡った右手が幸谷駅です。なんとも不思議な雰囲気があります。
「幸谷駅」から次の「小金城趾駅」までの、運転席からの2分ほどの動画です。ローカル線ならではの心地よい揺れと速度で、流鉄は進みます。
小金城趾駅(駅番号:RN3)

小金城趾駅(こがねじょうしえき)は、単線である流山線の全線で、唯一の列車交換を行う駅です。列車交換とは、単線を運行する上下線が駅構内や信号場に敷設した2線(以上)の線路を使って行き違う(すれ違う)こと。

ということは、小金城趾駅のホームには、必ず上下線の電車が入線しているこになります。鉄道が好きな人にはちょっとワクワクする駅ですね。
見どころ

駅名にもなっている小金趾は、駅から少し歩いた場所にある「小金城」の城跡です。「小金城」は戦国時代に下総国にあった、巨大な城郭を持った城で、豊臣秀吉による「小田原征伐」で落城しました。
鰭ヶ崎駅(駅番号:RN4)

ちょっと変わった名前の鰭ヶ崎駅(ひれがさきえき)です。その由来は、弘法大師が薬師如来を彫る際に、龍から捧げられた木に龍の“鰭(先=崎)”が残っていたという、近くの「東福寺」に残る伝説からとか、地形が魚の背鰭に似ていたからという説など諸説あるようです。
馬橋駅方面行きの「流星」号が入線してきました。電車が入線してきたというだけでワクワクできる魅力♫
この鰭ヶ崎駅から約1kmほど南西に行けば、1973年(昭和48年)に開業したJR武蔵野線「南流山駅」があります。2005年(平成17年)に「つくばエクスプレス」も開業し乗り入れていますから、少し歩きますが、JR・TX南流山駅と鰭ヶ崎駅を往復して、流鉄に乗り降りするという選択肢もありますね。
見どころ

●丸十パン店
駅の側には、1966年(昭和41年)に開業したという、ちょっと見逃せない「丸十パン店」があります。このパン屋さん、昔ながらの素朴で懐かしさ漂う美味しいパンを売っています。残念ながらこの日は、ご主人が腰痛とのことでお休みでした…。
平和台駅(駅番号:RN5)

平和台駅(へいわだいえき)は、新興住宅地(平和台)が広がる地域です。もともとは「赤城駅」という駅名で1933年(昭和8年)に開業した駅です。その後「赤城台駅」→「平和台駅」に改称しました。この地に「流山」という地名の秘密があります。
見どころ

●赤城神社

赤城神社は、駅から少し歩いた場所にある標高約15mの「赤城山」の山頂にあります。

この「赤城山」には、建長年間(1249~56年)に上州(群馬県)の「赤城山」の一部が崩れ、洪水によってここに土砂や、赤城神社のお札などが流れ着いたという伝承が残っています。これが『流山=ながれやま』という地名の由来となっています。
●一茶双樹記念館
一茶双樹記念館(いっさそうじゅきねんかん)は、元は“みりん”で流山の産業に貢献した「秋元家」のお屋敷です。“みりん”の商業化に成功した秋元家当主 五代目 秋元三左衛門(あきもと さんざえもん)は、秋元双樹の名で俳人としても知られ、あの著名な俳人 小林一茶と親交がありました。
一茶は晩年、この秋元家に50回以上も訪れていたといいます。そんな歴史から、秋元家を“一茶”ゆかりの地として、復原修理・整備し、1995年(平成7年)に“一茶”と“双樹”の名を冠して記念館としたものです。※観覧無料、月曜休館(祝日の場合は翌日)
★赤城神社

流山駅(駅番号:RN6)

流山駅(ながれやまえき)は、流鉄「流山線」の終着駅で、流鉄株式会社の所在地。駅舎は修理や改造が行われてきましたが、そのものは開業当時の1916年(大正5年)の建築で、「関東の駅百選」にも選定されています。

島式ホーム1面に2線があり、今日は運行していない「若葉」号が2番線に留置されています。

1番線はその奥にある検車区へ通じ、2番線は車止めで行き止まりになっています。
見どころ

甲子屋

甲子屋(きのえねや)は、流山駅から歩くこと約2分の場所にある1890年(明治23年)創業の老舗とんかつ店です。写真は特選ロースカツ定食。衣はサクサクの美味しい豚カツがいただけます。
★甲子屋

どうですか?短い区間ですが、100年の時を経て今なお現役の流鉄 流山線。歴史あふれるこの地域を、ローカル線に揺られて1日のんびり旅してみるのも楽しいものです。