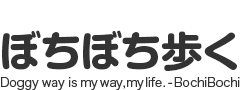東京メトロ銀座線、半蔵門線の「三越前駅」のB6出入口を出ると、そこはちょうど、日本橋北詰の東側「日本橋魚市場発祥の地」です。日本橋のたもとのこの周辺には江戸時代には魚市場発祥とされる「魚河岸(うおがし)」がありました。

ここには、それを記す石碑が立ち「乙姫様」の像も鎮座する「乙姫の広場」とも呼ばれている場所です。
日本橋の魚河岸は、日本橋川から隅田川に出て程近い所にある、あの佃煮で有名な「佃島」と深い関わりがあります。佃島は、もともと現在の大阪府大阪市西淀川区佃、江戸時代当時の佃村からやって来た漁民たちが1645年(正保2年)砂州に島を築き、定住しはじめたところです。

彼らが遠く大阪からやってきたのには歴史的にも大変興味深い訳があります。「本能寺の変」が起こった当時、大阪「堺」にいた徳川家康はわずかな手勢と供に、急ぎ本拠地である岡崎城に戻ろうと神崎川まで来たのですが、川を渡る舟が無くて困っていました。
そんな家康一行に、佃村の庄屋・森孫右衛門と彼の率いる漁民たちが漁船を提供してくれたおかげで、無事に岡崎に戻ることが出来たのです。後の1590年(天正18年)、家康が江戸に入る際に、その恩を忘れず、特別な漁業権を与えた上で彼らを江戸に呼び寄せたのです。
彼らは鯛など30種以上の魚介類を日本橋川など複数の経路で、江戸城に献上し、余った魚を日本橋の河岸で売る認可も受けていました。桟橋に横付けされた舟で商人と取引をし、魚は通りに面した店先で売られました。これが「日本橋魚河岸」のはじまりです。

そして江戸の人口は、爆発的に増えていき、日本橋魚河岸の商いは、諸国からの海産物も舟で集まるようになって行きます。海苔、佃煮、蒲鉾、鰹節など、今でも江戸から続く老舗が、日本橋に多く残るのもそうした理由です。

隷書版「東海道五十三次 日本橋」
1847年(弘化4年)
国立国会図書館
「錦絵でたのしむ江戸の名所」より転載
安藤広重51歳の作品です。魚を運ぶ商人や旅人などで賑わいを見せる日本橋です。遠方には富士山、右手には江戸城が描かれています。日本橋川沿いに建ち並ぶ蔵の多さや、運ばれている魚が立派なことからも、当時の日本橋魚河岸が活況だったことが想像できますね。
日本橋の魚河岸は、1923年(大正12年)の関東大震災で焼野原になり、その後の東京改造計画によって「築地」に移されました。諸国の魚介・海産物が沢山集まり、威勢のいい掛け声が響くのは、江戸時代から続いてきた魚河岸の名残、心意気なのでしょう。

鯛やヒラメが舞い踊る竜宮城の乙姫様からインスパイアされた像も石碑も、築地の魚河岸会が立てたもの。歴史を知れば、小さな「乙姫の広場」から見る日本橋と日本橋川の景色もひと味違って見えてきます。
日本橋魚市場発祥の地碑
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目8−1
日本橋

[ 広告 ]
ウルトラファインバブル生成《キッチン水栓》
ウルトラファインバブルは、超微細気泡の油分への吸着作用が油汚れにも効果を発揮《強力洗浄》します。またそのミスト水流は、肌にやさしく毎日の炊事での手荒れに効果的です。
どこよりも安い期間限定「平日ご優待プラン」が人気!圧倒的低料金でのプランが販売できるのは、通年で用意できるものではないから。