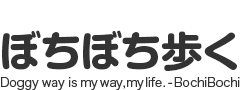JR御茶ノ水駅に沿うように南側を通る「茗溪通り」。中程にあるT字路を曲がった「お茶の水仲通り」を靖国通り方面へ向かいます。
途中にあるニコライ堂(東京復活大聖堂)西門を左手に緩やかな坂を下っていきます。その昔、この坂の辺りに池田姓の旗本のお屋敷があったことから、この通り・坂は「池田坂」と呼ばれています。

坂を下って行くと、目の前に大きな楠木(クスノキ)が見えてきます。そこが「太田姫稲荷神社」の門前です。

室町時代が終わるころ、関東一帯では天然痘が流行し、この地に居た太田道灌の娘もその病を患ってしまいます。

そのころ太田道灌は、京都の山城国(やましろのくに)にある「一口稲荷神社(いもあらいいなりじんじゃ)」が、このような病を治すという噂を耳にし、すぐさま使者を向かわせ娘の全快を祈願しました。すると願い通り、娘の病は治ったのです。

“一口(いもあらい)”の「いも」とは潰瘍の膿や血などを指す、あるいは「忌み」が変化したものとも。また「あらい」は「払い(祓い)」が変化したなど諸説ありますが、何れにしても太田道灌の見立てが功を奏したわけです。

太田家の家紋は桔梗(キキョウ)がモチーフ。丸で囲ってあるのは「太田桔梗」と呼ばれます。
その後、太田道灌は一口稲荷神を江戸城内に勧請し崇敬します。1457年(長祿元年)には、江戸城の鬼門に遷座され、それは「太田姫稲荷大明神」と呼ばれるようになりました。

ここで大事な事を一つ。ここまでの話からすると、“太田姫”という神社の名は、太田道灌の娘(姫)と考えてしまいそうですが、そうではありません。
一口稲荷神社は、太田姫命(おおたひめのみこと)と名乗る白髪の老翁から、疱瘡除けのため自身を祀るよう御神託を受けた小野篁(おののたかむら)が839年(承和6年)に創建した神社なのです。ゆえに「太田姫稲荷神社」という名なのです。
全国を平定した徳川家康は、1606年(慶長11年)江戸城増築に伴い、神社を聖橋の袂に遷座します。1931年(昭和6年)にはJR総武線の工事に伴い、今の土地に遷座しました。

太田道灌が娘の病の完治を祈願し、思いかなって創建された「太田姫稲荷神社」。祀られているのは娘では無く、太田姫命(おおたひめのみこと)と名乗る白髪の老翁、それに、文武の神として菅原道真公、徳川家康公が合祀されています。

緑豊かに再開発されている池田坂を下り、門前の楠木の大木を仰ぎ見、「太田姫稲荷神社」を詣でるのは心地良いものです。
太田姫稲荷神社
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1丁目2−3