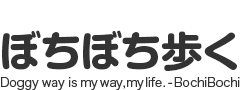東京駅の丸の内地下中央改札を出て左に折れ、しばらく歩いたところに「動輪の広場」があります。
慣れていないと目的の場所になかなかたどり着けない巨大な駅ですが、ここへは東京駅の地下にあるグランスタを、丸の内方面に進んで改札を出るという方法が一番わかりやすくておすすめです。

往来の激しい東京駅にあってか、立ち止まって見る人もまばらです。そんな「動輪の広場」ですが、色々知ってから行けば、ミュージアムの展示物と同様、見所が沢山で楽しく「鑑賞」できます。

この動輪は、終戦後に東京駅が修復されたのと同じ1948年(昭和23年)に製造され始めた、重量級のパワフルな蒸気機関車C62のものです。
翌1949年(昭和24年)までに全部で49両が製造され、輸送力が要求される東海道本線、山陽本線などの主要幹線を力走し戦後の日本復興を支えました。

プレートのC62 15の「15」は15号機を表します。東海道本線、山陽本線、函館本線などを、1971年(昭和46年)に解体されるまで約263万キロを走り続けました。

おりしも翌1972年(昭和47年)は国鉄創業100年を迎えた年で、新たに東京駅に完成した地下駅に、その力走の歴史をたたえるために、この動輪を飾ることにしたのです。

3つの動輪。1つの直径は1,750mmもある国内最大級の動輪です。素晴らしいのは動輪を動かした大事なメカニズムも一緒に飾られていることです。見ていきましょう。

左の壁から、真ん中の動輪に繋がっているのが「メインロッド」です。蒸気が入ったシリンダーがピストンを押し出し、このメインロッドを押すのです。そして真ん中の動輪が動きます。

手前のこれは「サイドロッド」です。前後の動輪にも動力を伝えるために、「メインロッド」から前と後ろに2本繋がっています。こうして3つの動輪が力強く動くという仕組みなんですね。

「メインロッド」と「サイドロッド」が繋がったここには、さらにマニアックなメカニズムが残されてます。いちばん手前にある部品です。無くてはならない「リターンクランク」という重要なものです。
本来は上にある穴に「エキセントリックロッド」が繋がっていて、車輪の回転で上下する動作を利用し、シリンダー内ピストンの前後に、交互に蒸気を入れる役割を果たします。
そう!だから蒸気機関車の「メインロッド」は前後ともピストン運動しながら常に動力を動輪に伝えることが出来るんです。

動輪の裏側も見ることが出来ます。解体されたC62 15ですが、動輪と供に残された「メインロッド」「サイドロッド」「リターンクランク」。
仕組みを知れば『これを残しておけば、いつかまた走り出すときに困らないからね。』というC62への愛情を感じざるを得ません。松本零士氏の「銀河鉄道999」のモデルでもあるC62。じっくり鑑賞している間は周囲のノイズは嘘のように消えています。
東京駅で有名な待ち合わせスポットの1つ「銀の鈴」

東京駅 動輪の広場
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9